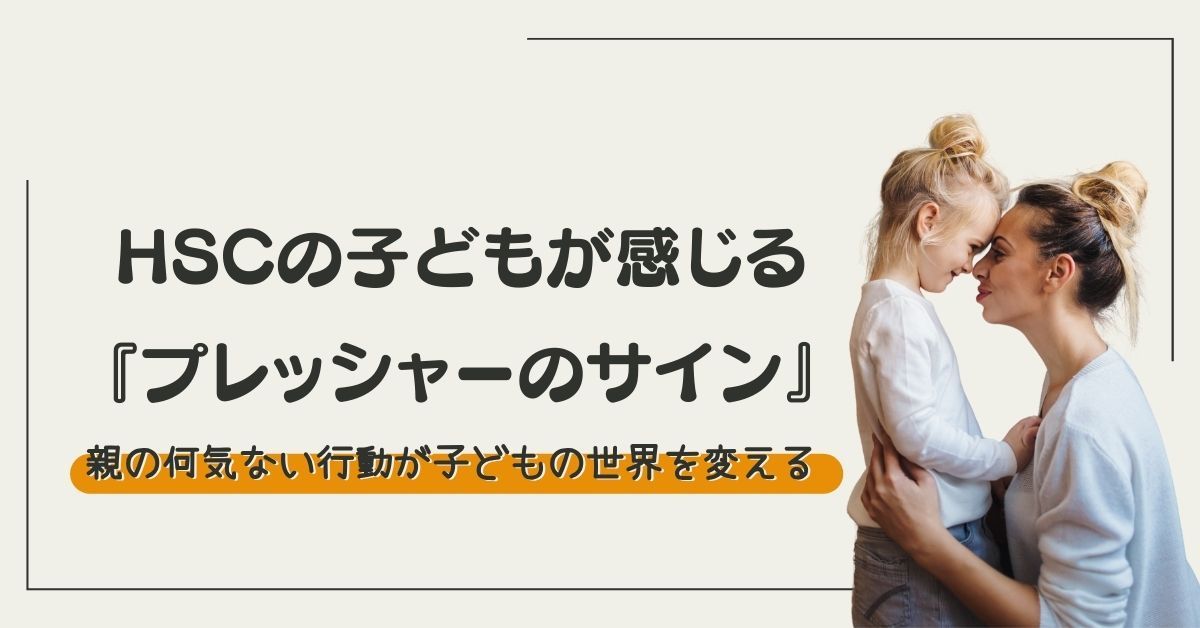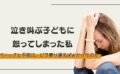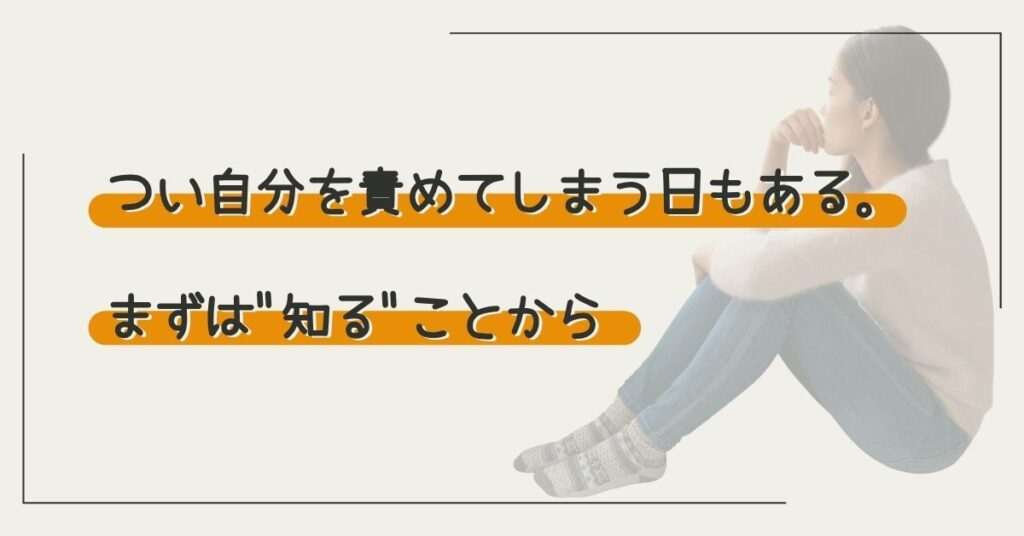
頑張っているのに、どうしてこんなにうまくいかないの?
「優しくしているつもりなのに、子どもが泣いてしまう。」
「励ましただけなのに、落ち込んでしまった。」
HSC(Highly Sensitive Child:とても敏感な子ども)を育てているお母さんなら、こんな戸惑いにも心当たりがあると思います。
子どもを思う気持ちは誰より強いのに、その思いがうまく届かない、、、。
「私の言葉がいけなかったのかな?」と自分を責めてしまうこともたくさん、、、。
けれど、それは”愛情が足りないから”なんてことではなく、届き方に差があるだけなんです。
ほんの少し、HSCの感じ方や受け止めかたの違いを知ることで親子の関係がぐっと穏やかになります。
この記事では、私自身の体験や学びから【子どもがストレスを感じやすい親の言動】について、今日から実行できる小さな工夫をお伝えしていきます。
「責めない」「待つ」「感じるを言葉にする」この3つがHSCの子どもの安心につながります
「責めない」―結果より”その日の小さな頑張り”を認める
子どもができないときに「どうして?」と理由を問うより、まずは今日できたことやその姿勢を認める言葉を!
「今日はここまでできたね」
「その気持を出してくれてありがとう」
この一言が心の安全基地になります。
「待つ」―話すタイミングは子どもが選べるようにする
敏感な子は、会話や質問のタイミングでストレスを感じることが多いです。
無理に話を引き出すのではなく”話したくなったら言える雰囲気”を作る工夫を!
朝の「行ける?」の声かけをやめる。
帰宅後すぐに感想を聞かないなど、、、。
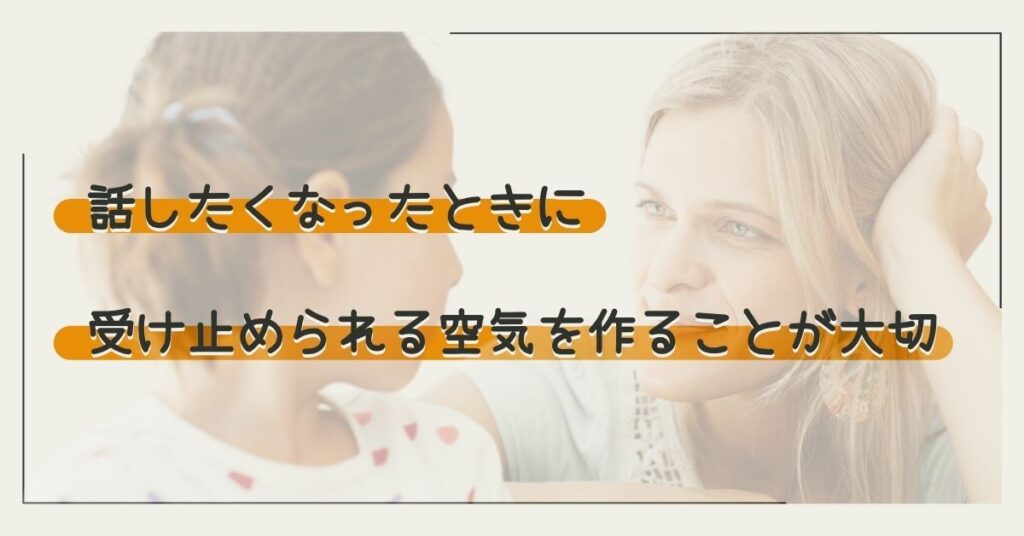
HSCの子が敏感に受け取る”親の言動”―具体的に何がストレスになるのか
HSCの子どもは言葉だけではなく、声のトーン・顔の表情・ため息・親の動揺などを敏感にキャッチします。
そのため、何気ない親の言葉や態度が、思った以上にストレスになることがあります。
「なんでできないの?」という責めに聞こえる問いかけ
「なんでできないの?」
「この前まではできでたのに、今日はどうしたの?」
これらの言葉は、つい口から出てしまうことはありますよね。
でも、HSCの子にとっては責められたこ感じやすく、”自分は期待に応えられない存在だ”と受け取ってしまうこともあります。
私自身も、娘が宿題を前に固まっていたとき、「昨日はこれできてたじゃん!」と言ってしまったことがありました。
娘は黙り込み、ポロポロと涙をこぼしながら自室にこもりました。
あとで「ちゃんとできないから、ママに嫌われたかと思った」と言われたとき、胸が痛みました。
子どもはできない理由を言葉にできないだけで”やりたいけどできない”と葛藤していることが多くあります。
そんなときは
「今日はどんな感じ?」
「何が一番イヤ?」
「疲れちゃったのかもね、ちょっと休もうか?」
と、気持ちに寄り添う言葉をかけてみてください。
子どもにとって”責められない安心感”が次の一歩を踏み出す力になります。
「元気に見えるのにどうして?」というすれ違い
HSCの子どもは、人前では頑張りすぎる傾向があります。
外では笑顔で過ごしてても、家で一気に疲れが出て涙が止まらなくなることも、、、。
親としては「さっきまであんなに楽しそうだったのに、どうして?」と戸惑います。
でも、実は頑張っていた分の疲れが、どっと出ている状態なんです。

・「今日はゆっくりしてね」と予定を軽くしておく。
・外出後は「お疲れ様セット(好きな飲物・静かな時間)」を用意。
子どもが安心して気持ちを出すようになりました。
“家でグズグズするのは甘え”と捉えるのではなく”外でがんばった分、家で安心して出せている”と受け止めることで親子の関係はぐっと楽になります。
親の「焦り」や「不安」が無言で伝わる場面
親が仕事や家事など時間に追われ疲れていたり、内心で焦っていたりすると、それが空気感として子供に伝わります。
そして、HSCの子どもはその空気感を自分の責任だと感じ取ってしまいます。
・子どもの前で「今は、ちょっと心配なことがあるけど大丈夫だよ」
・「ママ、5分だけ休憩するね」と親が休憩を取る姿を見せる。
このように、簡単な言葉や行動でいいんです。

“感情を出している”と子どもに示すことで、自分を責めてしまうことはなくなりますし、親への理解も深まります。
なぜ”その言葉”で子どもが傷つくのか―HSCの特性を親視点で理解する
HSCの特徴_感覚の鋭敏さ・深く考える傾向・他者の感情を容易に受け取る力。
“人の感情を自分のことのように感じる”特徴があります。
この特徴が、親の言動を”拡大解釈”してしまう原因になります。
感情を受け取りすぎるため「親の感情=自分のせい」と誤解する
親がため息をつくだけで「ママ、怒ってる?」と不安になることがあります。
だからこそ親が自分の感情を言語化することが有効です。
無理に笑顔を作るよりも「今日はママちょっと疲れてるだけ」と正直に伝える方が子どもは理解し、安心します。
細かい刺激に敏感_言葉選びだけではなく”環境”も影響する
照明・音・匂い・服のチクチク感など、日常の小さな刺激が積み重なって子どもの余裕を奪ってしまいます。
私たち親が「今日はいつもより静かにしよう」と周囲を整えるだけでも子どものストレスは下がります。
“やってみるリスト”すぐに実践できる10の工夫
すぐに実行できそうな具体策です。
どれも私が実際に試して効果を感じたものなので参考にどうぞ。
①朝の一言を変える
「今日学校に行く?」
(プレッシャー)
「おはよう!今日はどんな気分?」
(自分で選択できる)
②5分の”安全時間”を設ける
帰宅後や登校前に5分だけスマホを見せない・声をかけない時間を作り、子どもが自分の心を整理できるようにする。
③指示は一度に一つにする
複数の要求は混乱させてしまいます。
まず、一つ終わったら次、と分けて話しかける。
④具体的な選択肢を与える
「宿題やるよー!」ではなく、
「今やる?それとも30分後にやる?」と本人に選ばせる。
⑤感情語彙を増やす遊びを取り入れる
絵カードや感情ボトルを使って、日常的に”今の気持ち”を言葉にする練習をする。
⑥親の”本音の練習”をする
子どもの前で「今日はイライラしてる」「ごめん、少し休憩が必要」など、小さく自己開示する。
完璧である必要はないのです。
⑦小さな成功記録を作る
できたことノートを作り、5分でもできたことを書き留める。
自己肯定感が育つ。
⑧非言語サインで安心を示す
ハイタッチや目配せなど、言葉以外の「大丈夫」の合図を決める。
⑨事前に”中断のサイン”を共有する
刺激が強い場面で「もう限界」が来たら使えるサインを決めておく。(指を耳に当てる・親の服の裾を引っ張るなど)
我慢をさせすぎなきことに気遣う。
⑩親同士(支援者など)との共有ノートを持つ
学校やスクールの先生、祖父母など「子どもの安心につながる対応」を共有する。(短いメモでOK)

“やってよかった”子どもと穏やかに向き合う工夫
私自身がHSCの娘と向き合う中で、「これは効果があった」と感じた小さな工夫を紹介します。
朝の「行ける?」をやめて”選ぶ時間”を与えたら変わったこと
HSCの子は、疲れている時や気持ちが乱れているときに言葉をかけられると、どんな言葉も”責められている”と感じやすいです。
娘が不登校になり始めた頃、私は毎朝「大丈夫?」「今日行けそう?」と声をかけていました。
これが娘にとっては、プレッシャーでしかなかったんです。
そこで、朝の声かけを「おはよう!」「今日は何飲みたい?」などの何気ない会話だけに変えて、夕方には「今日はどうだった?」と感想を聞く時間も確保しました。
そうすると、自分から「今日は休みたい」「今日は、こんなことしたい」と落ち着いて伝えてくれるようになりました。
子どもが話したいタイミングを待つことも、立派なサポートでした。
親の”休憩宣言”で家庭の空気が変わった
日々の疲れやストレスなど、私が無言のままイライラを溜め込んでしまい、それが娘に伝わり落ち込んだり悲しくなったり、、、。
「ごめん!ママちょっと10分横になるね!」と宣言して休むようにしました。
あとからでも「さっきは疲れてて余裕なかったんだ、ごめんね」と正直に説明。
そうすると、娘も自分が原因ではないとわかってくれました。
むしろ「ママも疲れるよね、大丈夫?」と感情を共有してくれるようにもなりました。
気づきが、親子の安心を育てる
「この子のために、どうしたらいいかわからない」
でも、
「うまくいかない日もあるけど、ちゃんと向き合おうとしている」
それだけで、十分愛情を持って接しているお母さんです。
今日からできることは小さくてもいいです。
親の言葉や関わり方が少し変わるだけで、子どもは見違えるほど穏やかになります。
大切なのは”直そう”とするとではなく”理解しよう”とする姿勢。
・責めるより「気持ちを聞く」
・朝の問いかけを「選べる形式」
・焦るより「今できていることを認める」
・無理に笑うより「本音を伝える」
小さな工夫を続けることで、子どもは安心を取り戻し、親自身も少し楽になります。
今日の一文が、少しでも同じ悩みを持つお母さんの心を軽くできますように。