
不登校は”特別なこと”ではなかった

学校行きたくない。
小学2年の娘がそう言った朝、私は軽く受け流してしまいました。

たまたま疲れているのかも…
友達となにかあったかな?
その時の私は不登校という言葉をどこか他人事のように感じていました。
私が子どもの頃、学校を休むことは特別なことで風邪や冠婚葬祭以外の理由で休むことなんて考えられませんでした。
クラスの中に不登校の子がいた記憶もありません。
「まさかうちの子が…」
これが、不登校という言葉と現実に直面したときの正直な気持ちでした。
だからこそ、自分の子どもが登校できなくなることに現実感がなく、どう対応すればいいのかまったくわかりませんでした。
でも、その日をさかいに娘の「行きたくない」は続き、気づけば1週間…1ヶ月と時間だけが過ぎていきました。

どうして?
私の声かけが間違ってる?
きっとあの時の私は、子ども以上に焦りと不安でいっぱいでした。
でも今ならこう言えます。
不登校はどの家庭にも、誰にでも起こり得ること。
そこに親が自分を責めるべき理由はありません。
子どもを理解するには、まず”親が変わる”必要があった

私は不登校の娘を支える生活の中で大きな誤解をしていました。
『学校に戻れるように=正解』だと決めつけていたんです。
朝になれば声をかけ「そろそろ行ってみない?」と促す。
昼になれば「せめて勉強はしようよ」とまた声をかける。
でも、どれも娘の表情を固くし、言葉を奪っていくだけでした。
そんなとき「娘は私以上に不安を感じてるのかもしれない」と気づきハッとしました。
- 朝、布団から出られない。起き上がれない。
- 腹痛や頭痛を訴える
- 外からの音や声に敏感に反応する
それは、学校にいかない”理由”ではなく、すでに心と体が限界だという”状態”だったのです。
私は、学校に戻すことより、この子が安心して日々を過ごせることが何より大事なのだと学びました。
子どもが変わるのを待つよりも、まず私の関わり方を見直す。
それが第一歩となりました。
焦りと不安が空回りを生んでいた
私は最初、どうしたら学校に行けるようになるかばかり考えていました。

このままでは勉強が遅れる。
友達が離れていってしまう…
『学校に行かない=将来困る』と、強い不安でいっぱいでした。
だからつい「行かなくていい」と口では言いつつも、どこかで期待をしていたり

勉強これだけやっちゃおう!
と声をかけてしまう…。
でも、それは娘にとっては圧力でしかなかったんです。
当時の娘は、何をするでもなくどこに行くこともなく、常に周りの顔色を伺い、音や声に敏感に反応し、常に緊張状態でした。
学校に行けない子ではなく、心身が限界の子だったんだと今ならわかります。
私は、自分の考えを見直す必要があると気づきました。
“学校に戻すこと”ではなく”安心して過ごせる今”を優先する。
この視点の切り替えが、私たち親子の大きな転機になりました。
家庭でできることは、こんなにもあった
親が変わったきっかけ

不登校に関する本や体験記を読むうちに、
『親が不安を抱えていると、子どもにも伝染する』
という言葉が目にとまりました。
娘は、毎日なにもしてないわけではない。
必死に「どうすれば楽になれるか」を探してる。
まずは、その頑張りを見てあげなければいけなかったのです。
私が意識して変えたことはこの3つです。
- 朝「起きられたこと」に声をかける。
- 勉強よりも「好きなこと」に目を向ける
- 子どもと一緒に「今日できたこと」を話す
そうすることで、家の中の空気も少しずつ変わっていきました。
家の中での関わりが、子どもの安心を育てる

娘はダンスやメイクに興味がありました。
好きなアーティストやインフルエンサーの動画を見ながら毎日のように

今日はこれやってみる!
と自分の世界を広げるようになりました。
その時間には、学校生活のように「誰かに比べられること」も「正解を求められること」もありません。
自分のペースで試して、失敗して、楽しむ学びの場が自然と生まれていました。
YouTubeのダンスを見ながら振りを覚えたり、鏡の前で自分に似合うメイクを試したり…。
楽しんでいるように見える時間の中には、観察・工夫・表現がしっかり詰まっていました。
無理に机に向かわせなくても子どもは生活の中で、知る・考える・やってみるを繰り返しています。
親がそれに気づけるかどうかが、大きな分かれ道になると感じました。
不登校の中でも、新たな発見があった
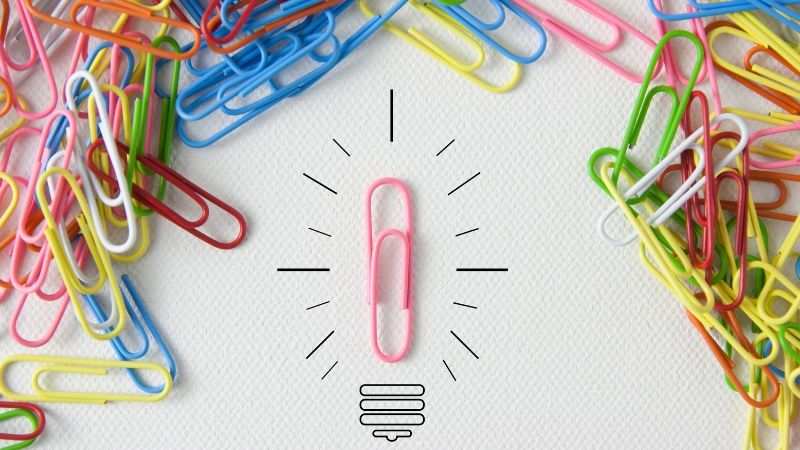
学校にいかないことで見えてきたことがありました。
それは、娘の本当の性格でした。
- 想像力が豊かで、ストーリーを作るのが得意
- 小さな動物や自然への感受性が強い
- 自分のペースで物事に集中できる
学校の中では評価されにくい”個性”が、家にいるからこそ際立って見えてきました。
不登校にならなければ、わたし自身も見つけることができなかったかもしれません。
子供の人生は”学校”だけでは決まらない

このままではダメと思っていたのは、私自身の不安からでした。
普通に登校できる子が「正しい」のではない。
登校できない子が「問題」なわけでもない。
不登校になったからといって「終わり」でもない。
子どもが学校に行けないと感じているなら、それはすでに精一杯のサインです。
親の理解と関わり次第で別の形の回復が必ずあります。
娘は今も学校には戻っていません。
でも、好きなことを通じて社会との接点を少しずつ増やしています。
勉強も自分のタイミングで進められるようにもなってきました。
学校に戻るかどうかではなく「この子らしく生きられているか」を大事にする。
この視点が持てたとき、私はやっと娘と同じ視点で歩けるようになりました。
学校に行くかどうかよりも、今心が元気かどうか
不登校は子どもが「今の環境では無理です」と教えてくれているサインです。
親としてできることはそのサインを無視せず、受け取ること。
受け取ったうえで「どう生きるか」を一緒に考えていくことだと思っています。
娘の不登校を経験して、私はこう学びました。
- 子どもは親が思う以上に傷ついて迷い、悩んでいる。
- 家庭でできることはたくさんあるし、学びの場にもなる。
- 「今、安心して過ごせること」が一番大事
- 学校にいかなくても、子どもは少しずつ社会とつながれる
そして何より親としてどうあるべきかを深く考えさせられ、学びました。
今、苦しんでいるお母さんへ。
「あなたは一人じゃないし、今すでにたくさん頑張っている。」と心から伝えたいです。




