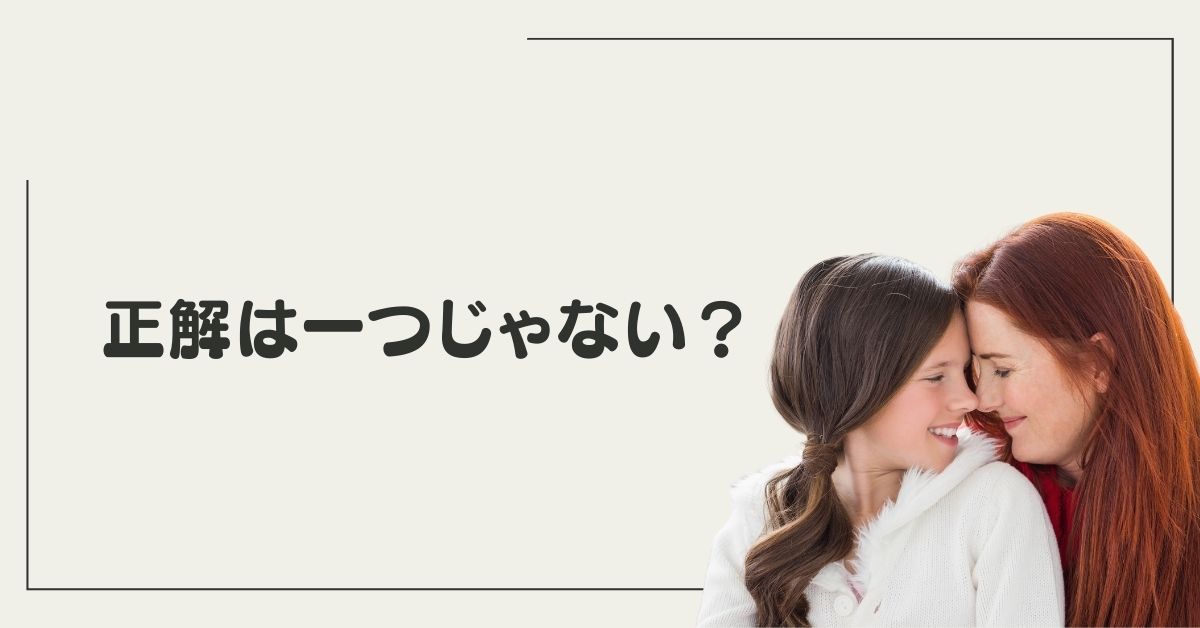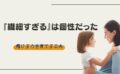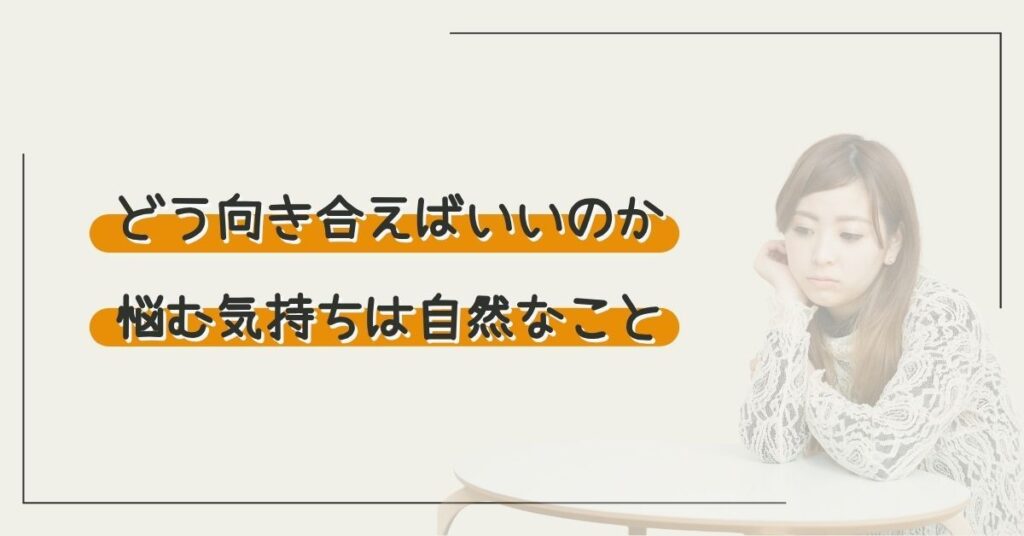
子どもが学校に行けなくなると、
「どうして、うちの子だけ学校に行けないんだろう?」
「私のせいなの?」
「休ませるのは、甘やかしてるのかな?」
頭の中がその問でいっぱいにいっぱいになり、息苦しい日がありました。
朝になると布団から出てこない娘。
声をかけても無反応。
無理に起こそうとすると声を荒げながら泣く。
私自身、娘が学校に行けなくなり『なにが正しいのか』『どう向き合えばいいのか』がわからず、毎日が手探りでした。
ネットにも本にも『解決策』は載ってるのに、どれも自分の子にしっくりこない。
「何を選べば正解なんだろう?」そればかり考えていました。
だけど、時間が経つにつれ確信したのは―不登校の向き合い方にたった一つの正解はない―ということでした。

今回は、私の経験から感じた「正解が一つではない理由」と「じゃあ、親はどう動けばいいのか」を、母親の視点でお伝えします。
不登校の向き合い方の”正解は一つじゃない”理由
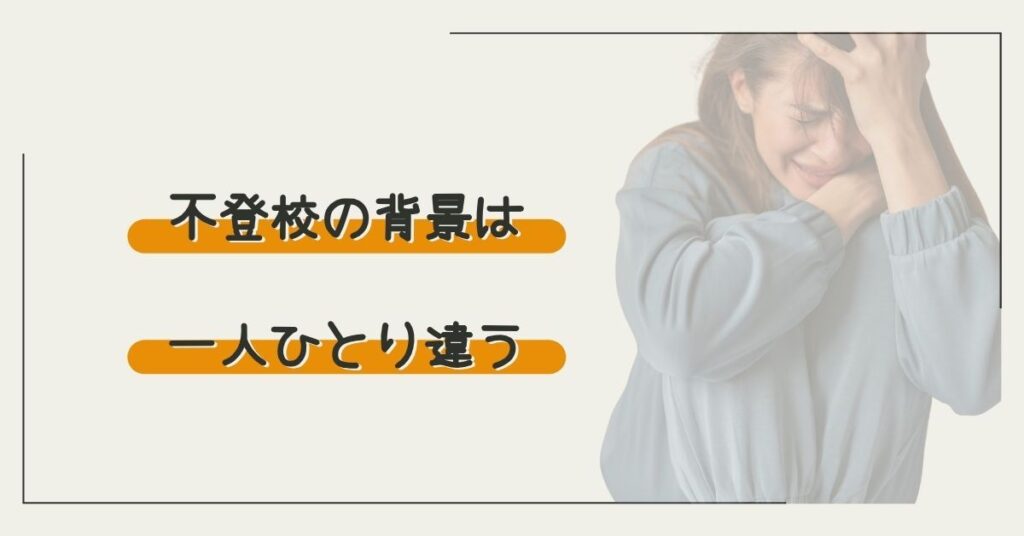
子どものつまずきポイントは一人ひとり違うから
同じ「学校へ行けない」でも、その理由はその子によって全く違います。
人間関係、教室の雰囲気、音・光の敏感さ、体調、完璧主義、不安…。
表に出る『不登校』という結果は同じでも、その奥にあるものは全然違います。
私の娘の場合は、他の人からは見てもわかりにくい感覚の過敏さが大きく影響していました。
・物音や大きな声に敏感で、教室のざわつきが耐えられない。
・人の視線や感情に過剰に反応してしまい疲れてしまう。
だから朝になると丸まって動かなくなり、小さな声で「お休みしたい」と不安な顔で伝えてくる…。
「行きたくない」ではなく「行けない」。
その差を理解するまでに時間がかかったのを覚えています。
だからこそ、効果的な関わり方も子どもによって変わります。
教科書通りの対応がそのまま正解にはならないのです。
親の状態も家庭の状況も「同じものはない」
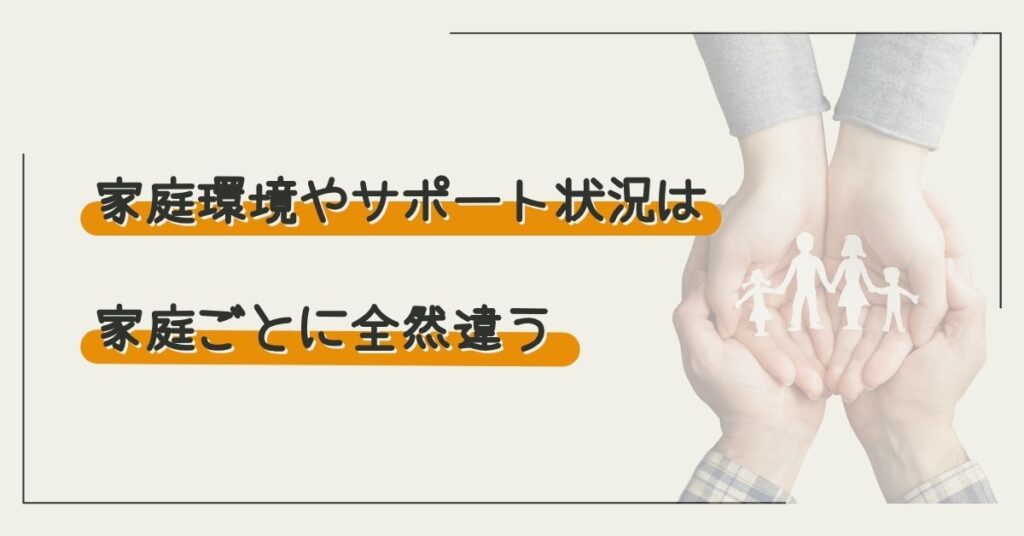
母親の体力・心の余裕、働き方、家族構成、サポートの有無…。
家庭ごとに”できること”は違います。
私もある時こう思いました。
「うちと全く同じ状況の人なんていないんだ」
そう気づいただけで、自分を責める時間が減っていきました。
親ができる”共通の土台”はある
正解は一つじゃないけど、どんな子にもどんな家庭にも共通して役立つ土台はいくつかあります。
ここからは、私自身が試してみて「負担が減った」「娘の様子が変わった」と実感したものを紹介します。
“今の状態”をそのまま理解することから始める
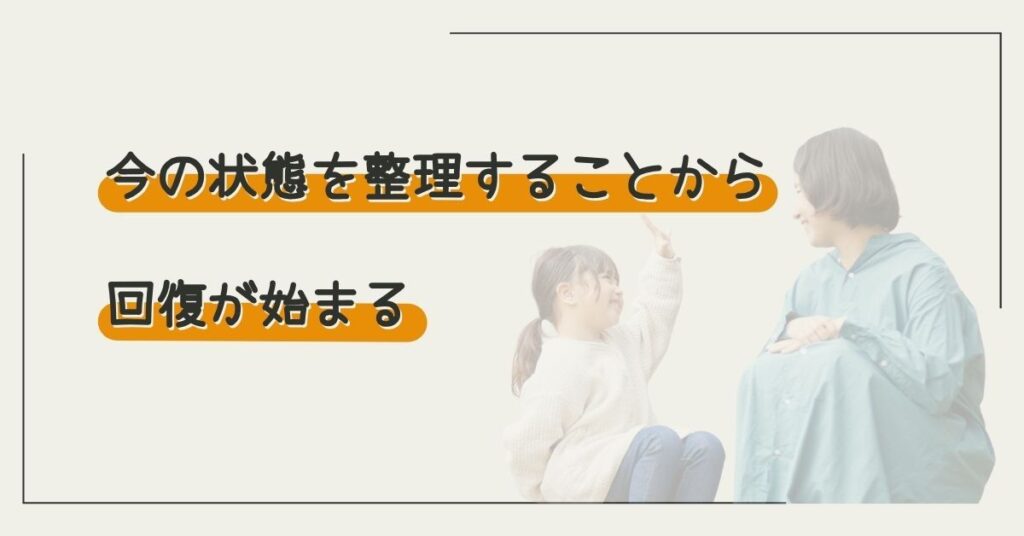
『どうしたら学校に戻れるか』 を考える前に、
『今、何がしんどいのか』を一緒に整理することが第一歩です。
私は娘との生活の中で気付いたことや変化をメモし、話せるタイミングで少しずつ共有してきました。
子どもにとっても「わかろうとしてくれてる」「見てもらえてる」という感覚は安心感にもつながります。
家庭を”安全地帯”にするための習慣をつくる
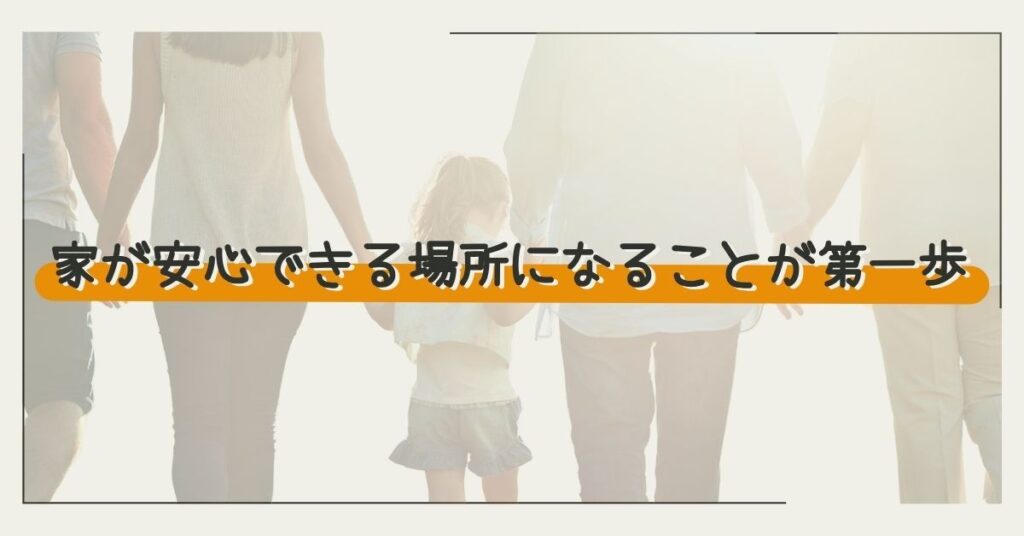
できることは本当に小さくて大丈夫。
・朝は慌てさせない
・理由を聞きすぎない
・帰宅後の「今日どうだった?」を控える
・失敗しても否定しない
などなど…。
その小さな積み重ねが「家なら大丈夫」という土台を作ります。
家で安心できなければ、学校どころじゃない。
家庭が整える場所になるとと、子どもは自然と自分のペースを取り戻し始めます。
実際に効果があった向き合い方
行けない朝は「できることだけ」を一緒に決める
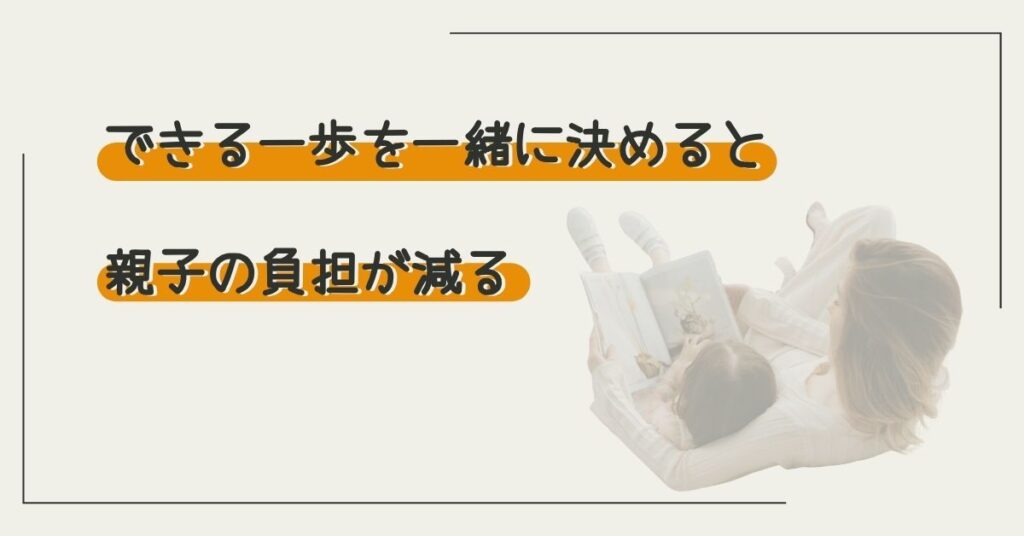
不登校になった当初、娘は布団から出られない日が続きました。
そこで私は、「学校に行く?」の質問をやめ、今日できることだけを聞くようにしました。
・一緒に朝ごはんを食べる
・着替えはしない
・外には出ない
・デザートを作りたい
なんだっていい。
ほんの小さな行動でも「できた」と言えた瞬間、表情が少し変わりました。
好きなものを「回復時間」として活用する
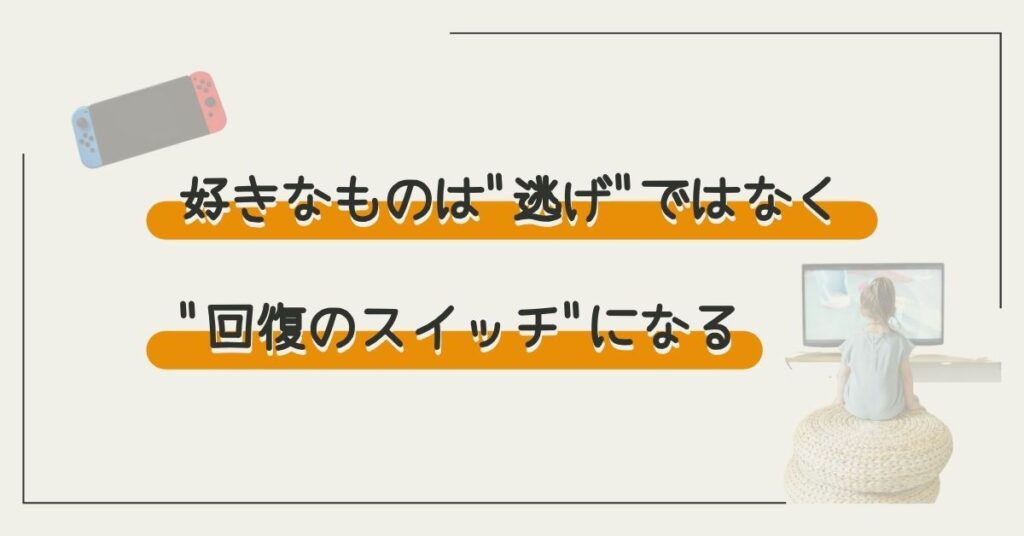
ゲーム、漫画、アニメ…。
これらは『逃げ』ではありません。
娘の場合はアニメとダンス動画がその役目を果たしました。
・気持ちを落ち着かせる
・学校の不安を忘れる
・次の行動へ切り替える
そんな心の回復の時間でした。
「ダラダラしてるようで、実は回復中なんだ」
そう気づいたことで、私の見方も大きく変わりました。
あなたの子どもに合う”方法”が必ず見つかる
不登校の向き合い方にひとつの正解はありません。
でも、あなたの子どもに合う形は必ずあります。
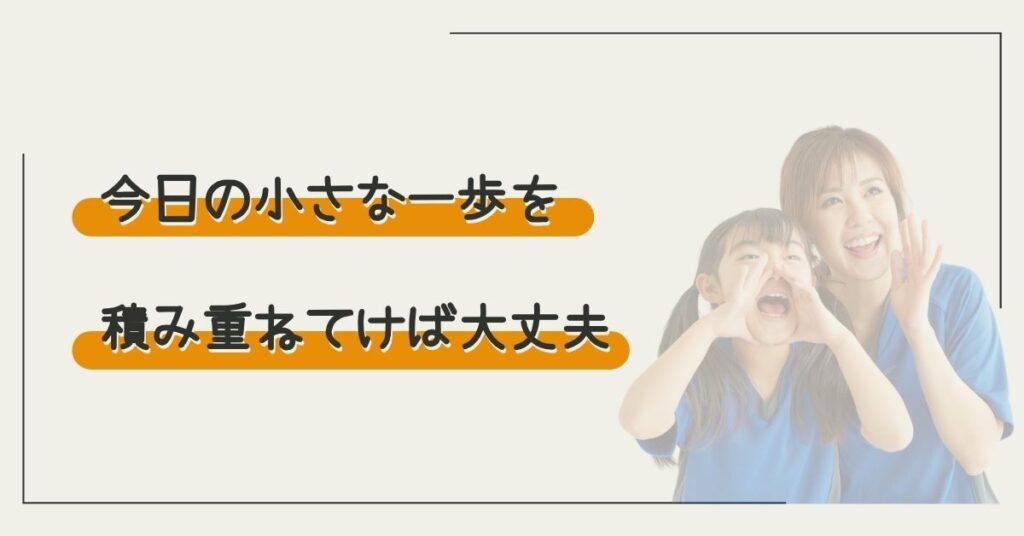
今日できる一歩は本当に小さくていい。
・話を聞く
・できていることを一緒に確認する
・しんどい朝は一つだけできることだけを決める
その積み重ねが、子どもの力をゆっくり取り戻していきます。
あなたもまた、毎日必死に手探りで頑張っています。
その努力も確実に子供どもの未来に届いていきます。