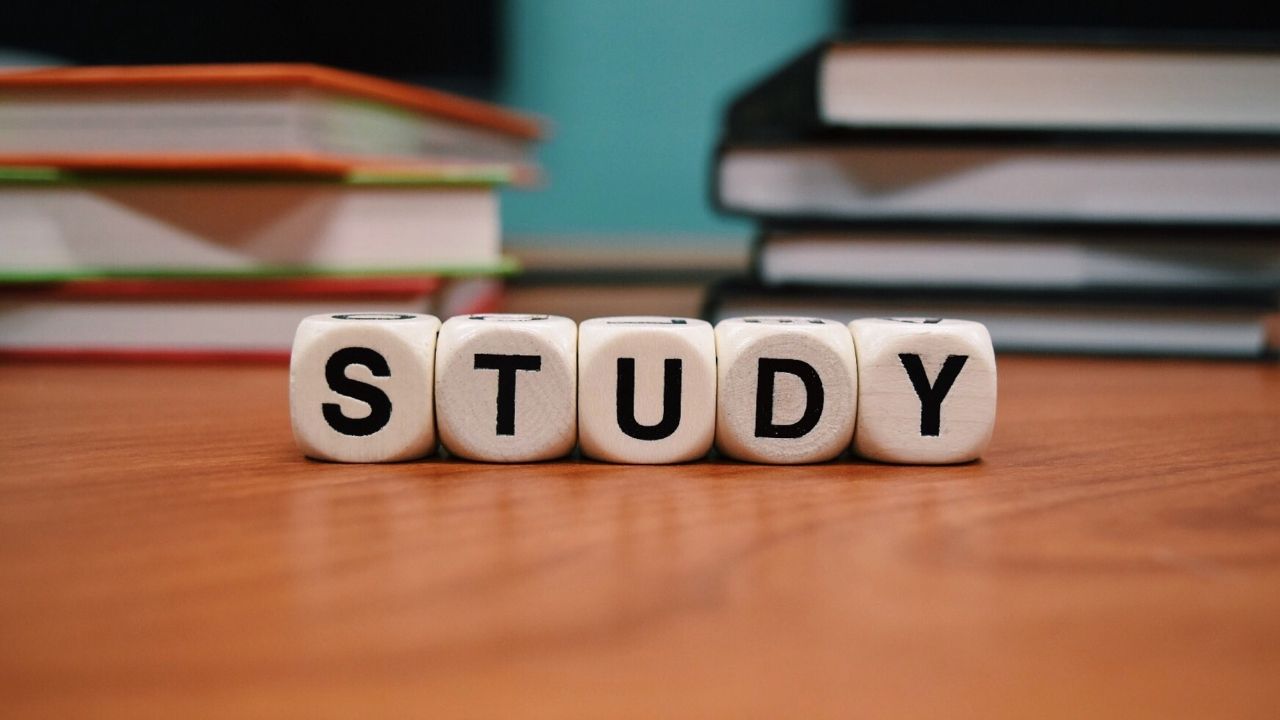不登校でも『勉強は必要』_だけど押し付けは逆効果
子どもが不登校になると、親として勉強の遅れが気になる…。
このまま勉強しなかったら将来どうなるの?
社会に出るときに困るのでは?
そんな不安からつい「勉強しなさい」と言いたくなります。
そして、勉強をしないことではこんなリスクも…
- 同年代の子と学力差が広がっていく
- 将来の選択肢が減るかもしれない
- 子ども自身ができない自分に落ち込む
何より学ぶことは子どもが社会に出る準備のひとつです。
勉強はただのテスト対策ではなく、考える力・表現する力・選択する力など将来必要になるスキルを育ててくれます。
だからこそ今できる範囲で、学びを止めないことが大切だと感じるようになりました。
でも、無理に勉強をさせようとすると子どもにとって勉強が「嫌なもの」「強制されるもの」になり、逆効果になってしまいます。
私たち親はどうすれば子どもに負担をかけずに勉強の大切さを伝え、将来に向けての道標を示してあげられるのか?
子どもを無理に動かすのではなく、『学ぶ力を信じて一緒に歩む』ための考え方と方法を考えて行きましょう。
勉強は『今すぐ』でなくていい。でも『遠ざけ続ける』ことは危険
不登校の子どもにとって、学校の勉強はたしかに負担に感じるものかもしれません。
でも、勉強そのものを避け続けることはデメリットが大きいです。
だからといって、無理にドリルをさせても続かない…。
ポイントは勉強は大事と伝えたうえで、親子で生活の中に学びを取り戻していくこと。
これは『無理やりやらせる』こととは全く違います。
子どもに「勉強しなさい」と言うのではなく「勉強するとこんなことができるようになるよ」とつ伝え、一緒に前を向いていく姿勢が大切です。
「勉強しないと困る」は抽象的。具体的に伝えることで子どもの納得につながる
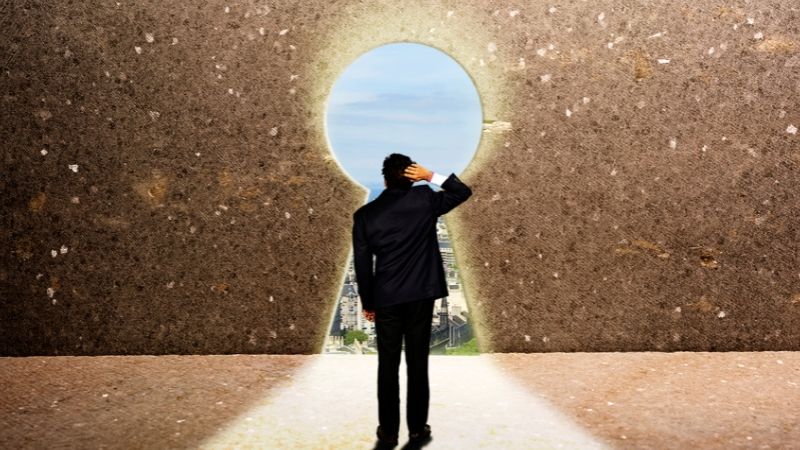

勉強しないと将来困るよ!
この言葉、私もよく使っていました。
でも娘には響きませんでした。
子どもにとって『将来』はぼんやりしていて、勉強はしなきゃいけないものだと言われるだけではなぜ必要なのかピンとこないんです。
だから私は勉強がなぜ必要なのか?を、娘の生活とつなげて伝えるようにしました。
たとえば
- 好きなゲームを攻略するには「読み取る力」や「数値の把握」が必要
- 動画編集には「時間の計算」や「構成力」が必要
- 将来「好きな仕事」を選ぶには、最低限の学力が必要
こうした身近な例と学びのつながりを知ることで、娘の中にも少しづつ

勉強って必要なことなんだ
と言う意識が芽生えてきました。
勉強は将来自分の進む道を自由に選べるようにするための道具。
社会に出たときに、自分の人生をよりよくするためのものなのです。
『なぜ必要か』を具体的に伝えることで、子どもが勉強に向かうきっかけになります。
親子でできる!『学ぶ力を取り戻す』ための3つのアプローチ!
①勉強と現実を結びつける話をする
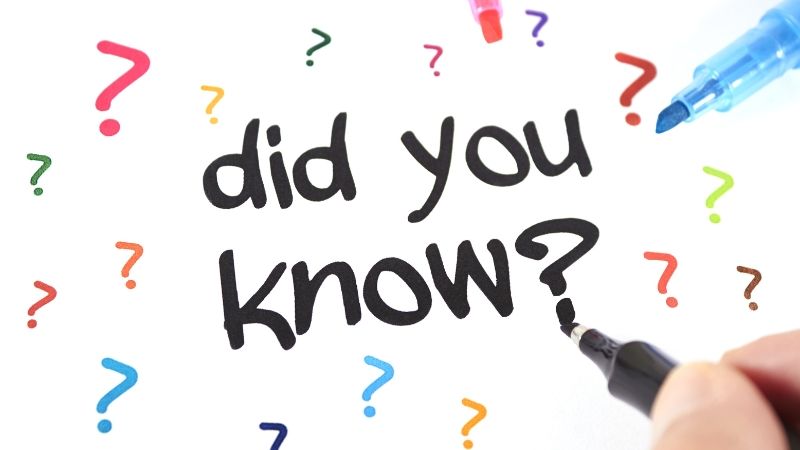
「将来のために!」と言われても子どもにはピンときません。
でも「こんなこと知ってる?」と好奇心を刺激されると、自然と興味を持ちます。
- 「お店で値札を見るとき、20%オフってどのくらい安くなるかわかる?」
- 「世界には、100歳まで生きる人が多い国と、少ない国があるんだって。なんでだと思う?」
- 「スマホやゲームの仕組みって、どうやって動いてるか知ってる?」
こうした日常の会話から「知ること=楽しい」と感じられると、勉強へのハードルが下がります。
② 子どもの興味を活かす

「勉強は大事だからやるんだよ!」では子どもに響きません。
でも、子ども自身が興味を持つことは、そのまま学びの入り口になります。
- ゲームが好き!!
→ ルールや攻略本を読む(読解力アップ)、ゲーム内の数値を計算する(算数の応用) - 料理が好き!!
→ 分量をはかる(算数)、レシピを読む(国語) - YouTubeが好き!!
→ 学習系チャンネルを一緒に見る(科学・歴史・社会の知識)
無理に学校の勉強をさせるのではなく、子どもの好きなことを通じて学ぶ力を育てることが大切です。
③できたことを認め、小さな成功体験を積み重ねる

子どもが勉強をする上で大切なのは「できた!」という成功体験です。
- 簡単な問題から始める(1日1問でもOK)
- 親が「できるようになったね!」と認める(「こんなこと知ってるんだね!」と興味を持つ)
- できたことを目に見える形にする(ノートに○をつける、カレンダーに記録する)
少しずつ「やればできる!」という感覚がつくと、子どもは自分から学ぼうとするようになります。
勉強は未来の自分のため

不登校の子どもにとって、勉強をすることは親のためではなく自分のためであると感じられることが大切です。
- 勉強は、将来自分の人生を自由に選ぶためのもの
- 知識があると困ったときに調べる力がつき、社会で生きやすくなる
- 子どもの興味を活かして、楽しく学べる環境を作ることが重要
勉強は点を取るためではなく、社会の中で自分らしく生きるための大切な準備だということ。
その意味を伝え、家庭の中で少しずつ学びを取り入れ、子どもが『学ぶ=価値のあること』と思える環境を作ることが私たち親の役割だと思っています。
『学び』は親が与えるものではなく、一緒に育てるもの

- 勉強は「テストのため」ではなく「生きる力」をつけるもの
- 社会に出るときに役立つ知識が身につく
- 「勉強しなさい」と言わず、日常の中で「学びの楽しさ」を伝える
- 子どもの興味を活かし、小さな成功体験を積み重ねる
親は学びを楽しむ環境を用意しましょう。
そうすると、子どもは自分のペースで学ぶ力を身につけていきます。
勉強をすることは、将来の自分を助けること。
そのことを、無理なく伝えていきましょう。