
髪を抜く子どもに、戸惑う親の気持ち
ある日ふと見ると、子どもの髪が少なくなってることに気がつきました。
「おかしいな?」と思っていたら、指で髪を引き抜いている娘の姿が…。

どうしてこんなことするの?
心配と戸惑い、少しの怒りが押し寄せてきたのを覚えています。
最初はどう対応すればいいのかわからず悩みました。
そこで専門家に相談し、少しずつ子どもの気持ちに寄り添えるようになりました。
このように自分で髪を抜いてしまう行動である『抜毛症(ばつもうしょう)』について、
- 病院ではどう対応してくれるのか?
- 私たち親にできることは?
私の体験を交えながらわかりやすくお伝えします。
抜毛症は心のSOS。抱え込まずに専門家へ相談

子どもが髪を抜いてしまう行為は、しつけや根性では解決できません。
子どもは甘えているわけでも、困らせたいわけでもない。
抜毛症は、心のストレスが体に表れている状態であり、医療機関での診断と支援が必要です。
髪を抜いてしまう子どもとの生活は、親として心配になったり、どう声をかけていいかわからなくなるかもしれません。
まずは、一人で抱え込まずに専門家へ相談してみることが、子どもにとっても私たち親にとっても安心につながる第一歩になります。
「やめたくても、やめられない」抜毛症の本当の姿
抜毛症(トリコチロマニア)は、退屈・不安・緊張などを感じたとき、無意識に髪を抜いてしまう症状です。
抜くことで一時的にスッキリしたり安心したりするため繰り返してしまうのが特徴です。
私の娘もこう言っていました。

やめたいけど、気づいたら抜いちゃってるんだもん。
でも痛くないよ?
本人もやめたい気持ちはあるのに、どうにもできない…
「やめなさい!」の言葉が逆効果になってしまうことも…
子どもを責めることなく、専門家といっしょにどう向き合っていくかを考えていくことが大切です。
親子で病院に行ってわかったこと

どこに相談する?
私はまず小児科を受診しました。
そこで症状と伝えると児童精神科を紹介されました。
小児科で診られない理由として「外傷・投薬での治療であれば診れるが、この症状は心の状態からくる症状であり、まだ小学生と幼いこともあったので心の回復を助けてくれる専門の病院で見てもらうのがいい」とのお話でした。
そして、児童精神科の初診まで2週間。
正直少しでも早く診てもらいたい気持ちが強かったので「そんなに待つのか…」と思ってしまいましたが、これでも初診までは早いとのことでビックリしました。
それだけ同じように悩む家族が多い事を知るきっかけにもなりました。
小児科→児童精神科・心療内科という流れが一般的。
予約制が多いので、まずはかかりつけ医に相談してみて下さい。
診察では何を聞かれる?
まずは娘の産まれてから今までの成長過程・食生活・家族構成・普段の行動の様子など数枚の問診票に記入しました。※母子手帳持参しました。
それから、親子それぞれの話を丁寧に聞いてくれました。
- いつから抜毛が始まったのか
- どんな場面で抜くのか
- 学校や家庭での変化
- 子どもの気持ちや不安について
娘自身も話せる範囲で医師と面談し、「どんなときに抜きたくなる?」「その時はどんな気持ち?」という質問に答えてました。
医師からは
- 抜毛症との診断
- 自分でのコントロールが難しい症状
- 長期的な支援が必要
- 娘に合う支援の方法をこれから一緒に考えて試していく
- 必要に応じてはカウンセリングや薬の処方がある
と、わかりやすい説明がありました。
娘の負担にならないような支援を一緒に考えていこうとの言葉に安心しました。
親にできること
①怒らず、事実だけを静かに伝える
「また抜いてる!」ではなく、
「今、髪触ってるね」と気づかせてあげるだけの声かけに切り替える。
②抜毛の代わりになるものを持たせる
ストレスボールや髪ゴム、ぬいぐるみなどてが寂しくならないように工夫するのも効果的。
③親自身も安心できる場所を持つ
私たちが思う「どうしてこんなことを?」というモヤモヤも、医師やカウンセラーに話すことで落ち着いて子どもと関われるようになります。
「一緒にがんばろうね」と伝えられる母でいられるために


私の育て方に問題があったのかな?
どこで間違えてしまったんだろう?
と、何度も思いました。
でも今は、こう考えています。
子どもは「助けて」って言えないかわりに、行動で私に教えてくれているんだと。
我が子のSOSに気づこうとしていること。
その姿勢があれば十分です。
笑顔のお母さんが、子どもにとって一番の心の支えになります。
抜毛症の子どもに向き合う親が知っておきたいこと
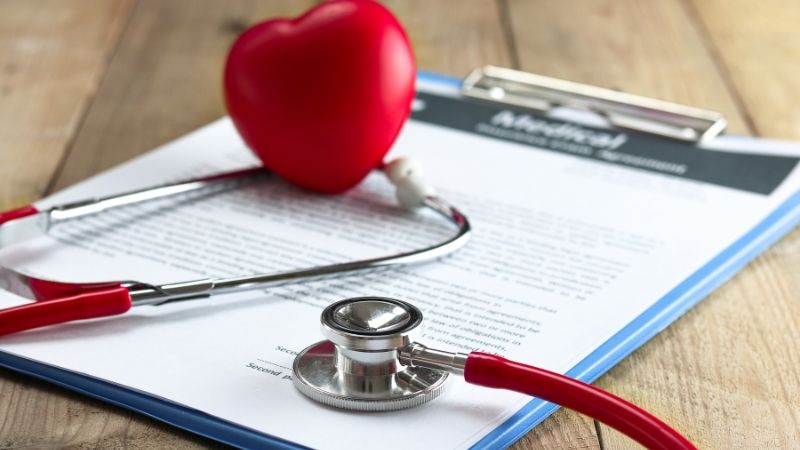
- 抜毛症は心の状態が表れた症状であり、医療的なサポートが必要
- 小児科から児童精神科・心療内科への紹介が一般的
- 『責めない・気づかせる・手の代替え行動』を親が意識する
- 親自身の不安は専門家に相談し、無理をしないことも大切
「この子をどうすればいい?」ではなく、
「一緒にどう過ごそうか?」と考えられる関係を築いていけたらいいですね。



